本文是一篇日语留学生论文,因为以被称为多产作家的柳美里的剧本和随笔等为主的纪实作品以及相当于“家族作品”的初期小说作为研究背景,所以在笔者在本文中证明庞大的研究背景的逻辑性的基础上进行作品分析的过程中我切身感受到了笔者对文学基础理论知识的匮乏。到处都应该有很多不完善的地方。不足的这些部分今后还打算继续研究。
第一章 序論
1.1 研究対象
柳美里は、1968 年 6 月 22 日茨城県生まれの在日朝鮮人女流作家であり、長編小説『家族シネマ』で 116 回芥川賞を受賞した。柳美里は日本文壇の中堅作家として活躍してきた作家であり、30 余年間の文学生涯の中で数多い文学的な変遷を経て今日に至っている。彼女の初期の文学は、家庭崩壊が主な文学的なモチーフであり、中期の文学は日本で生きている在日朝鮮人として脱民族的なテーマを取り扱っており、後期の文学は、民族的なアイデンティティを彼女の文学のモチーフにしている。勿論、まだまだ若い作家であるので、これからまた文学的な変遷を重ねながら柳美里文学は営まれていくのではないかと思う。
本稿では、柳美里のノンフィクション作品と『家族シネマ』をはじめとする初期の「家族もの1」を主な研究テクストとして、伝記的な文学批評理論を用いて、柳美里が経験した痛々しい家族崩壊の経験は彼女の心の中で如何にトラウマとして刻印されていき、彼女の心の中のこのようなトラウマはまた如何に芸術的に昇華して芸術作品として生まれ変わるかを研究することに本稿の目的がある。
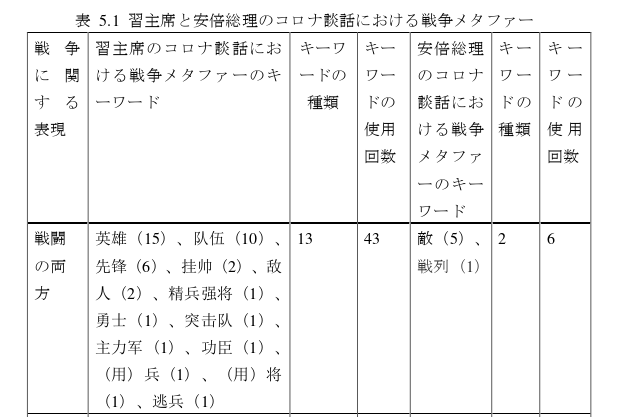
1968 年日本の茨城県出身の在日朝鮮人である柳美里は今年で 52 歳であり、デービュー以来に数多い文学作品を発表して日本文壇の中堅作家としての位置を固めながら活発な創作活動を行い、シナリオから小説やエッセイにいたる幅広い文学ジャンルの作品を大量に生み出した多産作家として其の知名度は高いものである。
1.2 先行研究
在日文学4は、在日朝鮮人によって日本語で書かれている文学であるということから、在日朝鮮人文学は日本文学の一部分でもあり韓国文学の一部分でもあると主張する人がいる。そのような意味から言えば、在日文学自体が二重性を帯びていると言えるだろう。その故で、在日文学に関する研究は、主に 90 年代以後日本や韓国を中心に行われてきており、最近は中国でも在日文学の研究が行われるようになっている。
日本における柳美里文学に関する学術論文を調べてみれば、以下の通りである。日本の文学評論家である秋山駿は、彼の論文「『家族シネマ』-崩壊家族とは?」5の中で、家族の絆が稀薄化している時代の社会現象として家族の意味を探ろうとしていると見るのが一般的な評価であると述べている。しかし竹田青嗣は、論考「異物としての生 柳美里『家族シネマ』」で、柳美里の固有のモチーフは家族であるが家族ということがテーマではないと主張する一方、切通理作や林浩治と共に或る意味の「在日性」という新しい意味付けを試みている。またトレイシー・ガノンも論考「「在日」を書く柳美里「在日」として書かれる柳美里初期作品を通して」6の中で、二重に集録化されたマイノリティ-7文学として新たな「在日性」の意味を付与しようとするなど、既存の在日文学と違う面での評価がなされている。林浩治は「民族を背負うことなく-柳美里『石に泳ぐ魚』の新しさ-」(1995)という論考の中で、在日文学のコンテクストに置いて考察する場合、「祖国を目指すという問題意識はこの若い作家にはない。韓国との関係は環境にすぎない。そしてその環境すなわち境遇に、作家の恨みを育むものを感じるのだ。柳美里は恨みを持っている」8と指摘した。
第二章 柳美里の不幸な家族での成長と文学及び言語観
2.1 柳美里の不幸な家族での成長と文学
1997 年、柳美里の自伝的な小説-『水辺のゆりかご』14が出版された。この作品は、三部立てとなっていて自伝の形式で彼女が誕生から 18 歳までの生活経歴を書き綴っている。第一部の「畳の下の海峡」は生まれて小学校卒業までが書かれており、第二部である「校庭の陽炎」は中学校から高校中退までか書かれており、第三部である「劇場の砂浜」はデビュー作である『水の中の友へ』が劇化されたまでの経歴を書いている。本章ではこの作品をもとに、柳美里の不幸な家族での成長を纏めている。
日本の文学評論家である野崎六助は、彼の在日文学に関する著書ー『魂と罪責』のなかで、柳美里の自伝小説ー『水辺のゆりかご』に対して以下のように書き下ろしている。
早すぎた自伝と称される『水辺のゆりかご』を二十代で問うわけだが、座りの悪さは変更できなかったのではないか。不安定とは少し違う。在日者のアイデンティティよりも常に、柳美里という単独の個性のほうが強烈に輝いてしまう。
誕生を語る「畳の下の海峡」という章題も、在日二世として特別の境遇を語るものではない。ポストモダン在日小説との近縁を見つけられるように、自伝そのものが価値を放っているのではなかった。人気作家の自伝という付加価値に支えられていたのだ。名前に関しても、漢字、読み方も、日韓両用に使えるという形であり、特別のものではなかった。
2.2 柳美里文学のアイデンティティーと言語観
2006 年柳美里は勉誠出版から『<在日>文学全集』に作品を収録することを勧められるが硬く断りを言う。李良枝と柳美里は同じく在日三世代文学者に分類されるが、二人の文学のモチーフはまったく異なる性向を持っていると言えるだろう。李良枝は民族アイデンティティへの葛藤や悩みを主なモチーフにしている反面、柳美里は脱民族的な創作活動をして来ている作家であると評価されている。
柳美里が韓国訪問の際、記者会見のたびに「なぜ、ウリマル(私たちの言葉)を勉強しないんですか?」と詰め寄られるが、そのような質問に彼女はこういう風に返事する。「わたしは日本人でも韓国人でもありません。日本語にも韓国語にも違和感をおぼえてきました。その違和感、言葉に対する過剰な意識こそが、わたしを書くことに向かわせているんです」18と返事する。また、「正直に言うと、自国の言葉を他国語のように学習するという屈辱を味わいたくないがためにプライドという固い殻をかぶっていただけなのかもしれない。」19と付け加えている。在日文学第一世代は、朝鮮民族としてのはっきりした民族意識を持っており、彼らにとって日本はあくまでも借りて住む臨時的な空間であり、朝鮮半島は何時かは帰らないといけない理想の地であったに比べて、在日朝鮮人第三世代文学者である柳美里は自分は韓国人でもなければ日本人でもない日韓の伱間に挟まれているマージナルマン(marginal man)20として自分を意識しており、またそういう風に自分を定義しているのである。在日朝鮮人という存在は、「うちとそと」文化が重んじられている日本という社会の中で、主流社会に溶け込むことができず、マイノリティー(minority)として定義されているのが現実である。その故で、上で述べてきたように柳美里は幼いときから「畳の下は海峡」であることを意識しながら生きてきたのである。
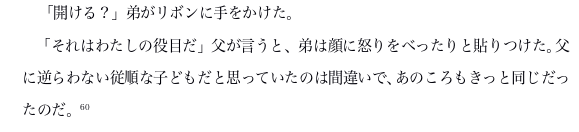
第三章 『家族シネマ』伝記的特性と家族崩壊のトラウマ...........................16
3.1 柳美里文学の伝記的な特性.................................... 16
3.2 柳美里の家族崩壊のトラウマと『家族シネマ』...................... 22
第四章 『家族シネマ』に見える家族の実態と虚像...............................31
4.1 『家族シネマ』に見えるシナリオの作家の面影........................................ 31
4.2 『家族シネマ』に見える家族の実態と虚像................................ 35
第五章 結論............................46
第四章 『家族シネマ』に見える家族の実態と虚像
4.1 『家族シネマ』に見えるシナリオの作家の面影
上記で述べてきたように、柳美里は小説家である前に一人のシナリオ作家であったことは周知の事実である。柳美里はシナリオの創作から始まっており、小説を書く前に彼女は既に 10 編ほどのシナリオを書いている。『水の中の友』で劇作家・演出家としてデビューし、1993 年に『魚の祭』で第 37 回岸田國士戯曲賞を最年少で受賞した。1994 年、処女小説『石に泳ぐ魚』を文芸誌『新潮』に発表し、小説家としての活動が始まった。この時期に柳美里は、自分が経験した家族崩壊の痛みを文学的なモチーフにしている一群の所謂「家族もの」を書き出すが、1995年に発表した『フルハウス』や 1996 年に発表した『家族シネマ』などがこれに当たる。彼らの柳美里初期作品には、柳美里のシナリオ作家としての面影が色濃く残っていると言える。
記で述べてきたように、柳美里は小説家である前に一人のシナリオ作家であったことは周知の事実である。柳美里はシナリオの創作から始まっており、小説を書く前に彼女は既に 10 編ほどのシナリオを書いている。『水の中の友』で劇作家・演出家としてデビューし、1993 年に『魚の祭』で第 37 回岸田國士戯曲賞を最年少で受賞した。1994 年、処女小説『石に泳ぐ魚』を文芸誌『新潮』に発表し、小説家としての活動が始まった。この時期に柳美里は、自分が経験した家族崩壊の痛みを文学的なモチーフにしている一群の所謂「家族もの」を書き出すが、1995年に発表した『フルハウス』や 1996 年に発表した『家族シネマ』などがこれに当たる。彼らの柳美里初期作品には、柳美里のシナリオ作家としての面影が色濃く残っていると言える。
『フルハウス』(1995.5)や『家族シネマ』(1996.12)といった作品は、かなりのデフォルメをほどこされた異常家族の物語だ。これらの作品における柳美里は、より多く劇作家だった。小説家として吟味した場合、まだ押しかけの借家住まいをしているような窮屈さが目立った。家族とはもともと異様な集団なのだと主張しても、テーマとしての新奇さには到らない。才気はいたるところに発揮されているが、要するに、奇を衒った自然主義小説以上のものとは読めない。
第五章 結論
以上、在日朝鮮人作家ー柳美里のノンフィクション作品と初期の『家族シネマ』をはじめとする「家族もの」を研究テクストとして、柳美里が経験した家族の破壊が彼女の胸の中でどのようにトラウマとして刻印されていき、作家のこのような家族破壊のトラウマがどのように芸術的に形象化されて小説になって行くかを本稿の中で究明してきた。
本研究を通じて、筆者は柳美里の初期文学にあたる「家族もの」は、作家自身が幼い時に経験した両親の不和と家庭の破綻が心の中のトラウマとなり、「家族もの」は作家自身の心の中の「苦悶」すなわちトラウマが芸術的に形象化されたものであると断定する。本研究を通じて、以下のような結論を導き出してた。
1)柳美里は、日本で生まれ育ち、日本人と同じ学校で日本式の教育を受けて育てられているが、日本の主流社会には溶け込まず根なし草のような存在である。日本社会では在日外国人として定義されており、法律的には韓国の国籍を所持している在日韓国人である。しかしながら、柳美里は他の在日朝鮮人文学のようにディアスポラ民族としての個人的なアイデンティティ葛藤やディアスポラ民族の喜怒哀楽を文学のモチーフにしているのではなく、脱民族的な書き方をしているということが言える
2)本稿の第一章の研究方法と視角のところで述べてきたように、文学と人間の心の中の「苦悶」は関わり深いものである。司馬遷の心の中の「苦悶」が『史記』を完成させているように、柳美里が幼い時に経験した両親の不和と家庭破綻は幼い柳美里の心の中でトラウマとして刻印されていき、このようなトラウマは柳美里初期文学の文学的な動機でもあり、また源泉でもある。柳美里は幼い時に経験した家族破壊の痛みを文学的なモチーフにしているので、柳美里は化の個人的な伝記的な特性が強い。
参考文献(略)
